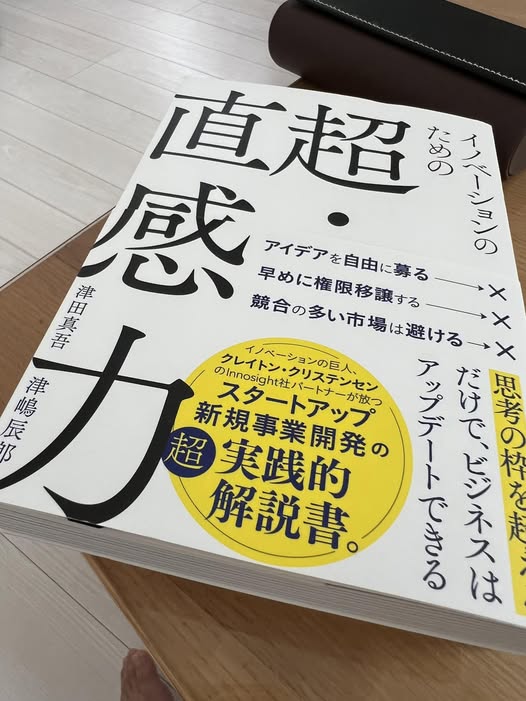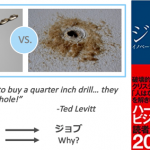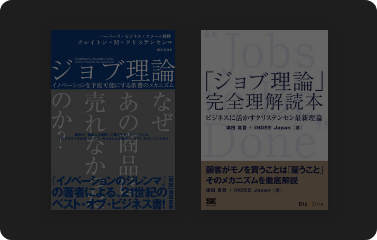これから何回かに分けて、人の持つバイアスやヒューリスティックについて書いていきたいと思います。『イノベーションのための超・直感力』出版のタイミングに合わせて書いておけばよかったなぁと「後知恵」(これもバイアス)ではありますが…
経済行動学という学問が生まれて以来、人間の脳にはいろいろなバイアスがあることがわかってきて、バイアスは大抵は早く結論を導いたり、脳が疲れすぎない効果があることがわかっている。つまり、バイアスは一般的な状況における判断を高速化・効率化するために人間に備わったもので、役立つ機能である。しかし、一般的な状況ではないとき、バイアスは逆に働く。行動経済学の多くの書籍は、こうしたバイアスによって間違った判断をしないよう、損をしないよう、注意する内容で書かれている。実際、行動経済学を巧みに活用したマーケティング手法や、詐欺まがいの販売方法も多数あるからだ。
そして、新規事業を立ち上げるというのは、一般とはかけ離れた状況である。
新規事業ではなかったとしても、チャレンジングな取り組みを成功させるには一般的な脳の使い方はマズい。例えば、難易度の高い大学に合格したいなら、脳の反応に任せてスマホの通知に反応するたびに志望校への合格は遠のくことは想像に難くない。
「ストイック」とは、特別な状況に追い込まれた特殊な状況を表す形容詞だが、難関大を目指すならむしろ当たり前だ。難しい新規事業にチャレンジしている方々が、既存事業のビジネススタイルやバイアスを「超えて」いくための手引書として昨年『超・直感力』を発表させて頂いた。
ということで、今回は「サンクコスト」について書いてみたい。
さて、人間の脳は色々なバイアスを持ちながら判断するのだが、ある意味そのバイアスは個性とも言える。例えば、完全に合理的な判断だけを行う(AIのような)機械があったとすると、「人間味がない」と見られるだろう。
バイアス、あるいはヒューリスティックにはたくさんの種類があるのだが、中でももっとも厄介なのが「サンクコスト」だと思っている。
というのも、人が「変わりたい」「成長したい」と考えたとき、邪魔になるのが習慣とサンクコストだからだ。
仮に片付けや物を捨てるのが苦手で、気が付くと家がガラクタの山になっている人がいるとする。時々そんな自分に嫌気が指し、一気に片付けて、いつも整った環境で暮らしたいと思い立つ。物を捨てようと、一つ一つのモノを触っていると、そのノスタルジーに染まっていく。苦労して買った品物や、思い出が染みついていると、まあ捨てられない。
組織も似たようなもので、DXと称して販売プロセスを電子化して効率化しようとする。ところが、要件定義をしながら、色々な「帳票」や「フォーム」「ハンコ」を“精査”しているうちに「このままにしておこう」「意味がわからないから触らないでおこう」「格式に合わせて様式も残しておこう」などと気持ちの変化が訪れ、またまた捨てられない。
過去に必要だったものが不要になったとき、「引退」するのがまともな道である。過去にどれだけ重要だったのかは、いったん脇に置いておこう。そんな判断が「引退」なのであるが、人間には難しい。過去の輝かしい時代を思い出してしまうし、手に入れたときの苦労はむしろ覚えていたい。この「手に入れた際に費やした過去のコスト」をその後も評価してしまうことを「サンクコスト」と呼ぶ。
さらに、過去の遺産をズバッと棄てたりすると「冷たい」という評価を浴びる。あるいは「冷たい人」だという評価を恐れて、棄てるのに躊躇する。
棄てる技術として、一時期「こんまり」こと近藤麻理恵さんの断捨離法が流行したが、とても優れた手法だと言えるだろう。というのも、過去のコストではなく「ときめき」という未来志向のワクワク感が欠如しているようなものを、近藤さんはバッサリ切り捨てるからだ。しかも、「サンクコスト」といった理屈や、合理性に訴えるのではなく、「ときめき」の欠如という人間的な感情に包まれた雰囲気を醸し出しているからだ。だが、近藤麻理恵さんは、そうやって合理的な判断をする手伝いをしているのかもしれない。古いものを捨てたときの何とも言えない寂しさをポジティブに昇華してくれる。
その点、AIには感情がない。片付けコンサルタントよろしく、似たような言葉をかけてはくれるだろう。捨てた方がよいかどうか尋ねてみたら、似たようなアドバイスをしてくれるだろう。だが、実際にモノを捨てることもしないし、捨てたときに人間が感じる寂しさや、悔しさは湧いてこない。
何よりも、「お前なんて冷徹に処分した心無い人間味のないモノだ!」と評価されたところで、痛みを感じることがないだろう。我々は、そんな評価を恐れた時点で大胆な決断ができなくなるというのに、である。
「こんまり」のような手法もあるが、人間はサンクコストというバイアスに勝てないのではないか、と思っている。
なぜなら「手に入れたときのコストを評価してしまうこと」自体が非合理的なのだ。そのコストを過大評価してしまうことではない。例えば、100万円で買ったA社の株と、1000万円で買ったA社の株、売るべきタイミングはどちらも同じだ。だが、1000万円をかけて入手した株には、いろんな思いが粘着していて手放し難いのが人間である。
私自身、塩漬けになっている株を持ち続けている。上場時、その会社のビジョンにとてもワクワクしたので購入した元ベンチャーだ。その後、その会社はビジョンの実現が難しいという事実に直面し、すっかりベンチャーとしての形も魂もない。株価は上場時の10分の1以下で、右肩下がりなので、早く売った方がいいことはわかっているのにも関わらず、売れない。「ときめき」は失われ、「思い」があるかといえばない。だが、処分しても消えない「悔しさ」のような気持ちは正直ある。その気持ちの元は、購入したときの経緯、そのときの期待やワクワク感なのだろう。些細な気持ちではあるが、「コスト」として引っかかっているのだと思う。サンクコストに勝つには、こうした些細な気持ちを忘れたり、未来志向で整理していく必要があるのだ。
だが、気持ちは気持ち、である。私のように小さな投資額であれば、サンクコストバイアスによる被害は少なくて済む。会社の経営、国の政策ともなれば、そうはいかない。多くの従業員や国民に影響を与えることになるだろう。要するに、判断や決断そのものは冷徹なものが求められることもあるかもしれないのだ。
人間はサンクコストに勝てない、と書いたが、複数の人間なら可能だととも思う。こんまりさんの問いをかける人や、損切りしたことで自由になるお金と時間を必要とする人。こうした未来形の問いがあれば、過去のコストを超える果実を得ようと動き出せるのではないだろうか。